 |
平成13年度に、サプリメントの安全性や有効性の確かな食品の選択と、正しい情報提供を目的として、「保健機能食品制度」が創設されました。この制度により、いままで法的規制のないまま販売されていた「健康食品」の中で、一定の条件を満たした食品に対して新たに「保健機能食品」と称する食品群が設けられました。
この保健機能食品は、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とに分けられ、特定の保健効果や栄養成分機能の表示内容が国で保証されているものをいいます。この制度が作られる以前の特定保健用食品は従来からある「特別用途食品」に組み込まれていましたが、この制度により保健機能食品の中に位置づけされるようになりました。 |
|
|
|
|
|
医薬品
|
特別用途食品
|
保 健 機 能 食 品
|
一 般 食 品
|
|
特定保健用食品
|
栄養機能食品
|
|
食品
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
乳児、妊産婦、高齢者、病者といった、特別な状態にある人たちの用途にあわせて利用される食品です。
乳児、妊産婦用食品には各々の発育過程に不足しがちな栄養素を調整した食品を、高齢者用食品には嚥下困難者用の食品などが認定されています。
病者用食品には高血圧の人が摂 |
る糖尿食調整組み合わせ食品などがあります。
個々の食品の許可基準に合格したものは厚生労働省の認定マークが表示されます。 |
|
|
|
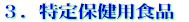 |
|
|
|
体の生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなど特定の用途のために利用される食品です。
これらの効能については厳しい審査をし、科学的根拠が認められた食品に対しては厚生労働省の認定マークがつけられ、保健用途の表示をして販売されます。
日常の食品と同じ形をとっており、ヨーグルト、清涼飲料水、食用油、ビスケット、ガムなど多くの食品があります。 |
|
|
|
その主な表示内容と保健機能成分は下記のとおりです
|
|
表 示 内 容
|
保健機能成分(関与成分)
|
| お腹の調子を整える食品 |
オリゴ糖 乳酸菌 難消化性デキストリン |
| 血圧が高めの方の食品 |
ペプチド類 杜仲葉配糖体 |
| コレステロールが高めの方の食品 |
大豆たんぱく質 キトサン 植物ステロール |
| 血糖値が気になる方の食品 |
グァバ葉ポリフェノール 難消化性デキストリン |
| 虫歯の原因になりにくい食品 |
マルチトール パラチノース |
| 体脂肪がつきにくい食品 |
ジアシルグリセロール |
|
|
|
 |
|
高齢化や不規則な生活により1日に必要な栄養成分をとれない時に、その補給のために利用する食品です。
現在、ビタミン12種類(A,B1,B2,B6,B12,C,D,E,葉酸,ナイアシン,パントテン酸,ビオチン)とミネラル2種類(カルシウム,鉄)が対象となっています。
厚生労働省が定めた1日の栄養成分量の基準にあてはまるものを「栄養機能食品」として、販売することができます。これは栄養機能表示や注意喚起の表示が義務づけられています。 |
| 食品に対するマークはなく、許可申請や届け出の必要もありません。これらは錠剤、清涼飲料水などの形で販売されています。 |
|
|
|
|
栄養成分の一部を、1日の摂取目安量と働きで見てみましょう。
|
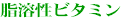 |
|
|
摂取目安量
|
は た ら き
|
|
|
1800IU
|
| ・皮膚や目の健康を維持する |
| ・ガンや生活習慣病を予防する |
|
|
ビタミンD
|
100IU
|
| ・カルシウムの吸収を促進する |
| ・骨や歯の成長を促進する |
|
|
ビタミンE
|
10mg
|
| ・冷えや肩こりを改善する ・生活習慣病を予防する |
| ・抗酸化作用の働きで老化を防ぎ若さを保つ |
|
|
|
|
IU・・・
|
International Unit(国際単位)の略称。ビタミンA・Dは重量での計測が困難なため、「効力」 |
|
を表すIUを単位としている。 |
|
|
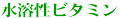 |
|
ビタミンB1
|
1.0mg
|
| ・糖質代謝に関与し、エネルギーを生産する |
| ・脳や手足の神経の機能を正常に保つ |
| ・肉体の疲労を改善する |
|
|
ビタミンB2
|
1.1mg
|
|
|
ビタミン C
|
100mg
|
| ・コラーゲンの合成に関与する ・免疫力を強化する |
| ・メラニン色素の生成を抑える ・ストレスを防ぐ |
|
|
|
 |
|
カルシウム
|
700mg
|
| ・骨や歯の形成に不可欠な成分 |
| ・ 緊張や興奮を緩和し、イライラを緩和する |
|
|
鉄
|
12mg
|
|
|
|
|
*
|
体内に入るとビタミンAに変わるもので緑黄色野菜に多く含まれています |
|
|
以上が保健機能食品の制度と種類です。表示内容や効果に対し、厳しい規制があります。それをクリアーした食品だけがこの食品群に含まれることになります。そのことから効果や成分量には信頼がおけるといえます。その上一般の食品と同じ形態をとっているものが多く価格差もそれほどないことから気軽に利用しやすいという利点があります。
ただ注意したいことは、この食品を摂っているから病気にならないというものではありません。一般の食品と同じ量を摂った時、上記のような効果が高まるという程度です。いくら保健機能食品だからといって普段の摂取量の2倍を摂っても効果が倍になることはありません。
その効果を過信することなく、あくまでも健康をサポートする「補助食品」としてうまく活用していきましょう。 |
|
|

